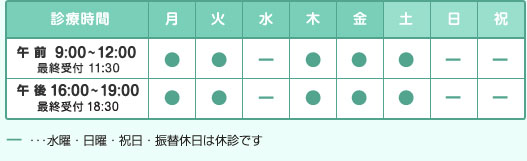フィラリア予防(蚊が媒介する死の病)
最初に相手を知ろう
フィラリアという虫は、犬だけでなくいろいろな動物に寄生する線虫であるが、犬に寄生するDilofilalia immitis という種類のフィラリアは、ラテン語で「残酷なフィラリア」という意味の名前のとおり、犬にとっては非常におそろしい寄生虫である。

急性フィラリア症の犬からつり出したフィラリア虫体。

この虫は、昆虫の蚊によって媒介され、最終的には犬の右心室から肺動脈にかけて寄生する。 寄生虫体の数が増加すると、心臓や肺の血液循環を阻害し、最終的には全身の血液循環不全に陥って、死にいたってしまうのである。
具体的な症状は、最初に軽度の咳から始まることが多い。 次いで咳の回数、強さが進行するにつれて、強い運動に耐えられなくなり、走らせると持久力が落ちてくる。 やがて、普通の散歩でも耐えられなくなって、散歩中にうずくまったり、あるいは卒倒したりするようになる。 そのうちに食欲不振になったりして、おかしいおかしいと思っているうちに、お腹が膨れてくるようになる。
心臓性の咳の特徴は、夜間に症状が増悪することである。 人間が寝静まった夜間に、苦しそうな犬の咳が限りなく続くのである。 咳が続くと最終的にえづきが生じて、嘔吐も観察される。 そのためフィラリア症が原因で来院するクライアントの主訴が嘔吐ということも珍しくない。
そうこうしているうちに症状が進行して、犬は呼吸が苦しくなって眠ることも出来なくなる。 腹水がたまって大きくなったお腹が胸を圧迫するし、肺の血管もボロボロになっていていくら息をしても酸素交換が出来なくなっているのである。

フィラリア症で腹水が溜まった女の子のビーグル犬。 腹囲は大きいが全身的には衰弱 して痩せています。 現在は内科的治療で何とかコントロールしています。


対照として、フィラリア予防をちゃんとしている健康なビーグルの画像です。
以上が慢性フィラリア症の症状であるが、フィラリア症にはこの慢性フィラリア症だけでなく、急性フィラリア症、あるいはケーバルシンドロームという別のタイプの症状もある。
このタイプのフィラリア症は、普通右心室から肺動脈にかけて寄生しているフィラリア虫が寄生数が多くなったり、外気温が急激に変動したりのさまざまな要因によって右心房から中心静脈へと寄生部位を移動することによって生じるものである。
このタイプは、まず赤いもしくはコーヒー色の尿の排出と、急激な右心不全による循環呼吸状態の悪化が特徴であり、内 科的治療にほとんど反応が見られないのが特徴である。 ではどうして治すかというと、左頚静脈から細長い鉗子を心臓まで差し込んで、フィラリア虫を釣り出すという、ある意味非常に乱暴な手術法で治療するのであ る。 この手術の成功率は、術者の熟練度にも拠ろうが、平均70パーセントだということである。 さて、私は何パーセントの成功率であろうか?
では飼い主はどうしたら良いのか?
フィラリア症は完璧に予防することができる。
どんな病気でもそうであるが、予防するほうが、罹ってから治療するよりも金銭的にも患者の負担からもはるかに有利である。
私の場合、第一選択にしている予防法は、4月から5月にかけて、まず犬の血液を調べて、フィラリアの寄生の有無を確認し、5月終わり頃から12月終わり頃までの間、月に一回予防薬を服用させるというものである。
フィラリア予防薬にもいろいろあって、毎日服用するタイプ、月に一回服用するもの、6ヶ月に一回皮下注射をするタイプ。 そして、2003年から販売されているものであるが、月に一回背中の皮膚に液をたらす蚤予防を兼ねるタイプのものも使われている。
毎日服用するタイプは、蚊が犬に吸血を始め出してすぐに服用を始め、蚊がいなくなるまで毎日錠剤を与えるものである が、飼い主の性格によっては毎日の投薬が負担になる場合もあり、現在では主流からはずれている。 しかし、月に一回よりも毎日の方がかえって忘れにくいという人には相変わらず良い方法であろう。
月に一回服用するタイプの予防薬は、錠剤、粉薬(散剤)、チュアブル(ご馳走の形で食べるタイプ)などいろいろな剤形があり、現在は手軽さ、安全性、予防効果の実績からこのタイプの予防薬が主流になっている。
6ヶ月に一回の注射薬は2002年に輸入されて、国内でも使用されるようになったが、使用開始間もなく、ショックを起こす症例が相次ぎ、現在ではほとんど使用されなくなっていると思う。 私も現在は使用していない。
月に一回背中の皮膚にたらすタイプ。 いわゆるスポットオンは、蚤予防を兼ねるタイプで、けっこう使えるかなとも思うが、しかし、私の開業する地域では外部寄生虫予防については蚤予防だけでは 不十分である。 貧血を起こすバベシア原虫の常在地では、マダニの予防も不可欠であり、スポットオンタイプのフィラリア予防薬が、蚤マダニ予防も兼ねることができるような れば積極的に使用しようと考えている。
で、私の動物病院で標準的に使用している月一回の投薬方法について少し詳しく解説すると、このタイプの薬は、いずれ も投薬後24時間たつと尿中に排泄されてしまう。 これが何を意味するかというと、一回服用するとその後一ヶ月フィラリアが入ってきても予防できるということではなくて、入ってきたフィラリア虫を服用した その時点で単に殺しているものであるということである。
つぎに心得ておくべき事項は、蚊によって媒介されたフィラリアの子虫は、入ったその時点では、この月一回の投薬では殺せないというということである。 この子虫は体内で約一ヶ月経過して、一回脱皮した時点でやっと薬で殺せるようになるのである。
つまり、この月一回の投薬タイプの予防薬は、春になって蚊が犬を吸血し始めてから約一ヶ月後から、秋も深まって吸血終了一ヶ月後まで服用しなければならないのである。
さらに、いずれのフィラリア予防薬にも共通のことであるが、投薬開始に先だって血液検査でフィラリアの寄生の確認が 不可欠である。 これは、昨年予防を実施していた症例でも大切なことである。 何となれば、フィラリア予防薬はいずれのタイプもすでにフィラリアが寄生している犬に何の予備的な処置も施さずに投薬すると、ショックを起こして、甚だし きはそのまま死亡してしまうからである。
もしすでにフィラリアが寄生してしまった個体でも、事前にショック防止の薬を投薬して予防を実施すればほとんどの症例で安全に、更なるフィラリア虫の侵入を防ぐことができるのである。
そして、さらに注意すべきこと
獣医師によっては、フィラリア予防薬として牛や豚の駆虫薬で同じ成分の水薬を希釈して、月に一回の予防薬として処方している場合も見受けられる。 この場合は獣医師が自らの責任において薬の適用外使用をしているのであって、必ずしも獣医療法違反でもなく法的には適正な行為ではあるが、しかし、このよ うな薬は希釈後の安定性が悪く、保存状態が悪いといちじるしく効果が落ちるのである。
このような薬は非常に原価が安いので利益率が良く、どうしてもそのような薬を出すという誘惑にかられるものではあろう。
しかし、そのような予防薬を処方しようと思えば、クライアントに対して、適切な保存方法とか十分な説明が必要であろう。 少なくとも私はフィラリア予防にそのような薬を使用するつもりはない。
ついで、投薬前の血液検査をしない獣医師も少なからず見られるが、そのような獣医師の許から転院してきた患者さんに、予防しているにもかかわらずフィラリアに罹患している症例が時々ではあるが見受けられる。 やはり手抜きは良くないと思う。
やはり何事においても基本に忠実であるということが大切ではないかと思うものである。